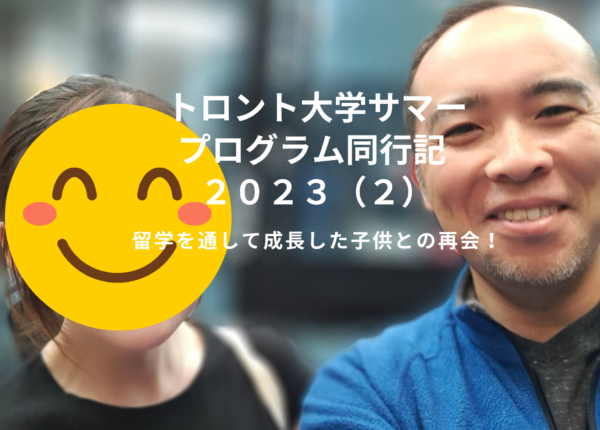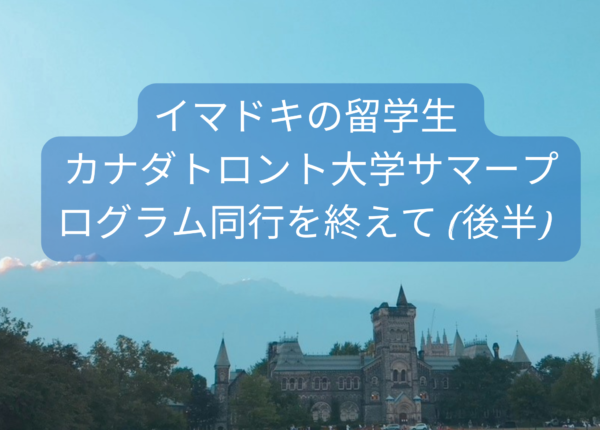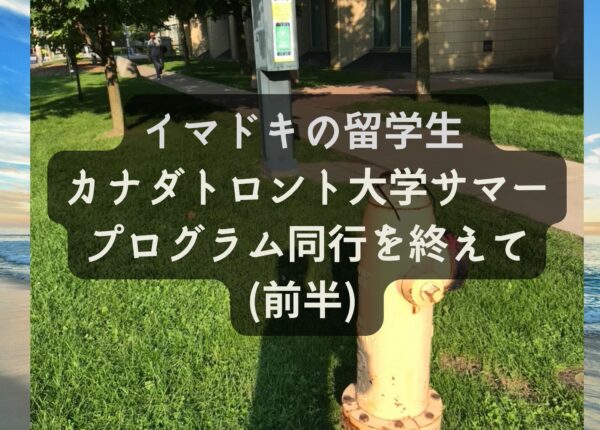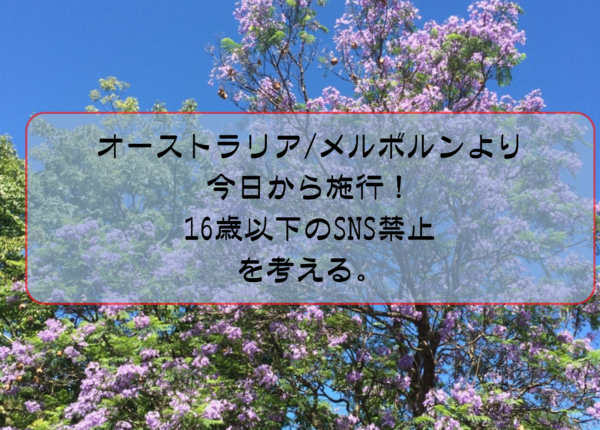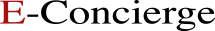トロント大学サマープログラム 定点観測 時代とともに変わる子供達と 留学の在り方について

ここ数年、ずっと工事中だったメインキャンパス前の芝生のグランドが今年からやっと解放されて、生徒たちや地元民の憩いの場に。
今年もトロント大学の中高生のためのサマープログラムの同行のために1週間、トロント大学の学生寮に滞在をしていました。10年以上にも及ぶトロントでの定点観測ですが、今年も多くの発見がありましたので、このブログ内で共有をしたいと思います。
今年のトロント便の人の多さ、サマープログラムに参加をする子どもたちの多さに驚いた事については前回のブログで書きましたが、今回もう一つ面白い出来事がありました。
トロント大学のサマープログラムは海外渡航が初めての子供達もいるので飛行機内でも対応ができるようにいつも比較的通路に出やすい場所に席を確保してもらっています。今回も非常口のある、前に席がなくスペースのある場所、3人席のちょうど真ん中に座りました。
すると、お隣の男性の方が「トロント大学のサマープログラムですか?」と声をかけてきました。
予想をしていない声がけに最初は呆気に取られていましたが、彼はすぐに私の首からけているIDカードにある「トロント大学プログラム」の文字に気付いてのことである事を理解して、「ああ、そうですよ!」と返事をしたところ、実は彼はトロント大学の卒業生で、トロント大学の文字に懐かしさを感じて声をかけてくれたようです。
それだけであれば、まだ偶然として良くあることかもしれませんが、もう一方に座る乗客からも声をかけられ、「私もトロント大学の卒業生です」との事、これにはもう3人とも笑うしかありません。よほど楽しそうに3人で話していたからか、離陸準備のために正面に座るCAさんも話に加わり、何ともにぎやかで楽しいフライト体験となりました。
私を除く3人はトロントに住むローカルのカナダ人でしたが、自分たちが学生時代を過ごした大学、そしてトロントにわざわざ訪問してくれる事を心から嬉しく思っていることが伺え、何度も訪問しているトロントでありながら、とても新鮮な気持ちで到着することができました。
前置きが長くなりましたが、ここからは生徒たちの定点観測です。
コロナ前に大問題となったスマホ問題については毎年取り上げる必要があるくらい、このデバイスの扱い方は毎年異なった潮流があり非常に興味深いトピックの一つとなっています。
第一印象として、
まず、子どもたちは授業や集団行動時に指示を仰ぐときなどはスマホをいじっている子供はコロナ前と比べると極端に減りました。つまりそれは、子供達はスマホの使い方について、世界共通のアカデミック環境における一定のマナーが浸透してきているように見えました。世界規模で学校と先生方が努力していることが生徒たちの振る舞いから窺い知ることができます。
また、以前はゲーム機であり、動画を見る手段であったスマホは留学という特殊な環境においては、自己表現のツールであり、生徒たちはその年代の子供達が持つ共通のコミュニケーションアプリを通して親交を深めていることがわかります。数年前の生徒たちのスマホには自己完結的なゲームがたくさん入っていたことでしょう、今の子供達にとってその割合はオンライン交流機能のあるアプリに切り替わっています。
「What is your name? Do you have an Instagram account?」
(名前はなんですか?インスタグラムのアカウントはありますか?)
これが、今の子供達の留学中のスタンダードな自己紹介の方法です。
カウンセラーも生徒たちとの連絡手段としてInstagramを当たり前のように利用しています。
スマホ世代のポジティブな部分。
生徒たちはプログラム前半については特に国ごとにまとまることが多いのが多国籍プログラムの特徴でもあります。当たり前のことですが、知らない国、文化圏の子供達と話をするのは精神的ハードルが高いのは当然のことです。ところが、今年の生徒たちはどうでしょう、3日目くらいから早くもいろいろな国の生徒たちが同じテーブルを囲んで、スマホの画面を見せ合って話しています。ちょっと覗いてみたるすると、一緒にショート動画を見て楽しんでいるようです。
私が留学をしていた二十数年前、スーパーマリオブラザーズの音楽を一緒に歌って、クラスの一体感が一気に高まった体験を思い出しますが、彼らはその比ではない量の共通の話題をすでに手元に持っているようです。共通の話題、共通の趣味がある事ほど、子供たちにとって嬉しいことはないでしょう。精神的なハードルを比較的簡単に乗り越えた生徒たちが、今年はとても多かったことが印象的です。
それでもやはり、スマホは万全ではない。
それでも一定数は、今までのようにスマホを片手に孤独を紛らわせている生徒がいることも事実です。スマホを手元に置いて、少し周りに目を向ければ違う景色があ流のにも関わらず、とても勿体無い事です。
今回、実際に私が見た生徒のお話も少ししていきましょう。
ケース1)韓国からの留学生。
私は基本的に一人で食事をとっています。誰でも必要な時に私に話し掛けてもらいやすいようにすることが目的ですが、そこに一人の韓国人の男の子がやってきました、大体13歳くらいの年齢でしょうか?
彼はとにかく一生懸命、英語で私に話し掛けています。まだまだ拙い英語ですが、彼曰く、「ここで韓国語で話をしては意味がない、今は友達はいないけれど、英語を勉強しに来たのだからこれで良い。」とのこと。それでも一緒に来た妹が一切顔を合わせてくれないことにショックを受けている可愛い側面もありましたが、孤独を恐れずにひたすら英語を話し続ける彼を見て、昔の自分が少し重なりました。私は彼の勇気を讃えたいと思います。
きっと彼はこの3週間で誰よりも多くの英語を話すことになるでしょう。
ケース2)メキシコからの留学生。
今回出会ったメキシコの生徒は物静かで自ら話しかけるタイプではない、同時に孤独をネガティブに捉えていない節もあり一貫している。それでも、率先して他の生徒のためにドアを開けて待っていたり、決して閉鎖的な態度を見せているわけではない。そして、彼はメキシコからの生徒たちが母国語で話しかけても、英語で返している。
彼の態度から、彼がこのプログラムに来た理由が明確に感じられたのです。これはとてもシンプルな事ですが、彼は英語を話すためにトロント大学に来たのです。それが静かに、明確に伝わったので私はどことなく彼を観察していました。そうしたら、どうでしょう、同じ意思を持つ子供達、最初は同じメキシコ人だったと思いますが、母国語ではなく英語で話していました。そして数日後にはその輪がだんだんと大きくなり、英語を話す輪が彼を中心に出来上がっていました。
私は、つい先日のブログにおいても「孤独の対処方法」についてブログを書きました。今回紹介した二人は孤独感を恐れることなく、安易にスマホの画面に逃げることなく、正面から孤独に立ち向かった対価として、本来の目的である「英語を話す」環境を自ら手に入れました。
次回に続く。