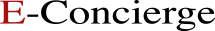留学物語-父は東大、ぼくはニュージーランドその3:母の憂鬱
(その2:2月28日掲載)
ぼくの母は美しい人だ。その母をぼくは日本の高校在学中に憂鬱にさせた。帰国子女枠の入試で入学したが、学校になじめなかった。なぜ勉強するのか、先生の説明によると大学受験を突破するためだそうだ。早慶を目指せという。最低でもMARCHなどと言っていた。なぜ早慶かという質問をする生徒はいなかった。先生によると、「大学に入ってから考えろ」だそうだ。問答無用の学校文化に適応できる帰国子女がいるのだろうか。
母には済まないと思っている。父同様、東京の私立女子大学を出た母だが、帰国子女というぼくたちの学校への不適応に具体的に対処することはとても大変だったと二十歳をすぎたぼくは思う。母はOLの経験がなかった。社会で人間関係にもまれたことも、経済的自立することもなく父と結婚した。そんな母は、ぼくのこころが日本の学校から離れ、地域から遠ざかって行くなかで、ただ悩み、そして沈黙していた。母は決して日本の進学校の価値観をぼくに強制することはなかった。その点では確かにぼくを認めていてくれた。日本の学校という組織にわが子の生い立ちや、その異文化体験を理詰めで説明しても、「学校の規則は規則ですから」と言われれば、反論はできない。勝ち目はないとわかっていたが故に母の憂鬱は根の深いものだった。優しさゆえの沈黙。もちろん、当時のぼくはそのような母のこころの苦労などわからなかった。
ぼくが強烈に望んでいたものは誇れる学校、地元とよべる地域、そして心が落ち着ける家だった。しかし、現実は好きとか嫌いとかでない無条件の勉強。それが中心にぼくの生活は組み立てられなければならなかった。先生は受験戦争という競争社会で勝利をつかむための短期決戦を強いていた。そのための戦略からはじまり、作戦をたてて、どんどん進んでゆく。勝利を望まない生徒、勉強に疑問も持つ生徒は相手にされない。ぼくは、勉強を頭から否定しているのではない。ただ、覚えさせられ、結果が悪いか良いかで先生の態度も変わるというのがおかしいと思っている。
ぼくの体験した海外の学校にはカウンセラーがいた。勉強とはまったく独立して生徒や親は自由にカウンセラーと話すことができた。自分を認めてくれる人が学校にいることで、安心できることもたくさんある。こころの支えはとても大切だと思う。しかし、日本の学校では、ぼくは誰とすなおに思うところを話したらよいのだろうか。ぼくの意見をまともに聞いてくれたのは何らかの理由で学校からはじけてしまった生徒たちだった。
つづく