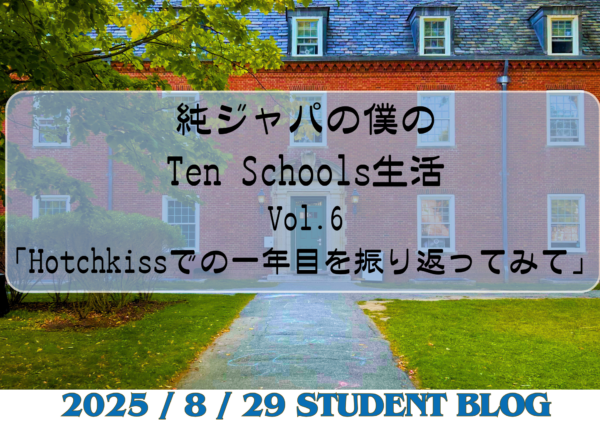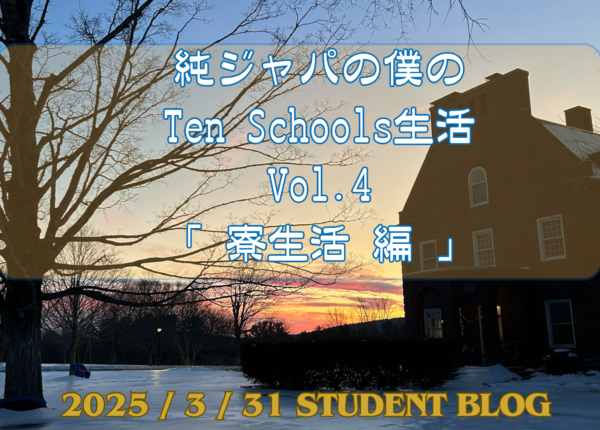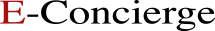2025/5/3 純ジャパの僕の Ten Schools生活 Vol.4 「 ディスカッションベースのクラス編 」
第5回 ディスカッションベースのクラス
5月に入りこれまでの寒かった天気から一転、気温も一気に上がり木々も綺麗な新緑へと移り変わる季節になりました。急に暖かくなった影響か、僕自身も冬以上にクラスやスポーツに対するモチベーションが上がってきた今日この頃です。さて5回目となった今回のブログは今まであまり話してこれなかった授業風景について話したいと思います。特に日本ではあまり見られないディスカッションを中心としたクラスの特徴やそれがどのように自分の興味に合っているのかについて共有したいと思います。
まず、日本の学校との大きな違いとしてクラスサイズが挙げられます。多くの日本の学校ではそれぞれのクラスが大体30人くらいかそれ以上というのが一般的かと思われますが、Hotchkissをはじめとする多くのボーディングではクラスサイズは多くても15人程度で、中には5人未満しかいない比較的人数の少ないクラスサイズが特徴です。
そのような少ない人数で行われる授業だからこそディスカッションベースの授業を円滑に行うことが可能なのだと感じます。加えて、日本の学校と違い自分のクラスが存在せず、教科ごとに違う教室、クラスメイトと学ぶことも最初かなり違和感を感じました。特にグループワークの課題が多いHotchkissでは特定の誰かとだけではなく多くのクラスメイトとクラスを通じて知り合えることがより強固なcommunityの形成につながっていると感じます。

ハークネステーブル
さてクラス内でのディスカッションについてですが、EnglishやHistoryなどの文系(Humanities)のクラスに加えてMathやScienceといった理数系のクラスでもディスカッションが頻繁に行われることがHotchkissの大きな特徴だと感じます。
Englishの授業ではハークネステーブルと呼ばれる楕円形のテーブルを約12人の生徒と先生が囲み、様々なトピックについて互いに議論しあいます。Historyのクラスではディベート対決もよく行われ、つい先週の授業ではアメリカの1960年代の市民権運動でMartin Luther King Jr.は大統領令に反して抗議行進を続けるべきか否かについて討論しました。
さらにJohn Rockefellerの石油会社が独占禁止法に違反しているか否かについて討論しあった疑似裁判(Mock Trial)では本格的に弁護士や証人、裁判官をそれぞれ決めて白熱した討論を数日間にわたって行ったこともありました。ちなみに僕自身はその模擬裁判ではTeddy Roosevelt元大統領として検察官と協力し、見事Rockefellerや弁護士を相手に勝訴できました。
一方で、理数系のクラスでもHumanitiesのクラスと同様に教室を囲むようにして、クラスメイトがお互いの方向を向き合うようにして授業を行います。Mathのクラスでも黒板に向かって先生の説明を聞き各々が問題を解く日本の学校とは対照的に、先生の説明を聞いたのち4人一組で向かいあって話し合いながら問題を解くという大きな違いがあります。そして、Scienceの授業のようにグループになってプレゼンテーションやレポートを作る機会の多いクラスではお互いの意見や知識を活発に話す機会が多く、それぞれのテーマに対するより深い理解を得られます。
ディスカッションベースのクラスのメリットは、自分が今まで思いつかなかったようなアイディアや観点をクラスメイトから吸収できることです。
特に世界中から来た違った価値観やバックグラウンドを持った生徒たちと話し合うことで、より創造的なアイディアを生み出せるという強みにもつながっていると思います。また先生が一方的に教えるのではなく、先生がクラスのリードをしてその後生徒が自主的にディスカッションを進めていくところを先生が観察してアドバイスをする、という授業の進め方の影響で僕含めて多くの生徒が言われる前に行動を始められる自主性を持つようになることもディスカッションベースのクラスだからこそと思います。
どのようなロジックで考えそのアイディアや答えを導き出したのかをお互いに共有し、理解できていないことを先生に聞く前にクラスメイトに聞いて教えてもらうという生徒同士の密な関係性が、Hotchkissの強固なCommunity valueにも大きく影響を与えていると思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。近況報告としては、自分のメインスポーツでもある野球のシーズンが始まり、打球をより遠くに飛ばすために体を大きくしようと思い、友達と週3で早起きしてジムに行こうと決めました💪