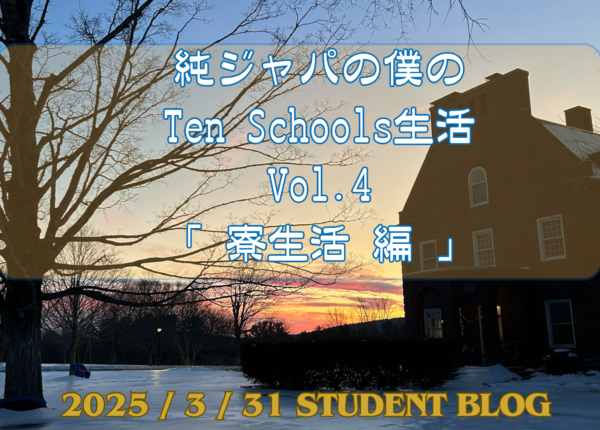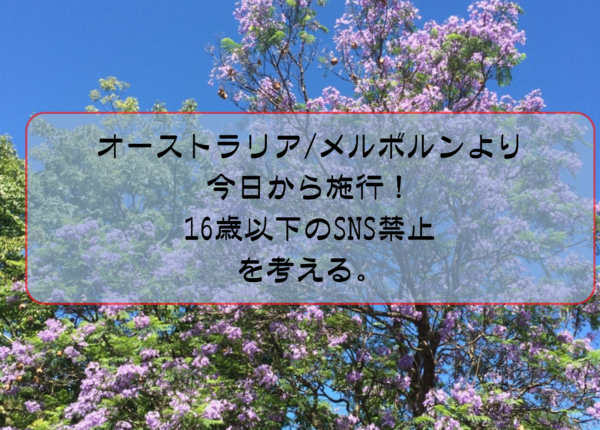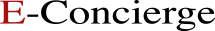純ジャパの僕の Ten Schools生活 Vol.6「Hotchkissでの一年目を振り返ってみて」
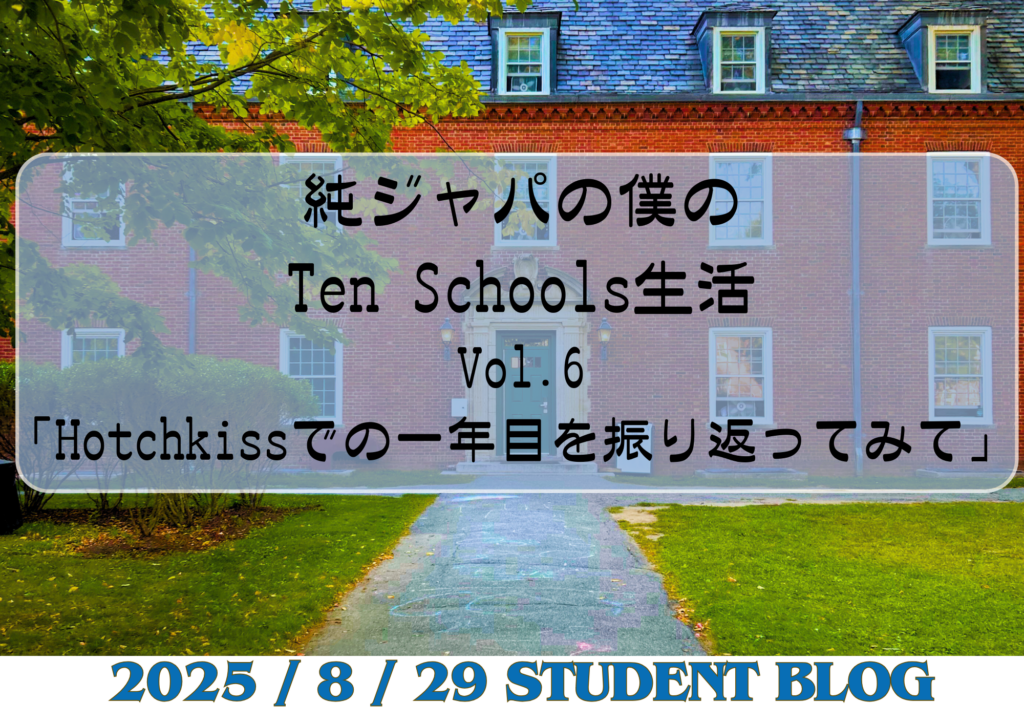
Hotchkissでの一年目を振り返ってみて
皆さん、お久しぶりです。夏休みに入り、日本に一時帰国をして久しぶりに友人たちと会えたことを喜ぶのも束の間、今はSAT(大学共通テスト)の勉強や学校の課題に追われています。今回のブログでは僕自身のHotchkissでの1年目を振り返ってみて良かった点、悪かった点、または驚いた点などについてお話ししていきたいと思います。
まず、全体的にみて僕の1年目の学校生活はかなり充実度の高い密な生活になったと感じています。ちょうど1年前の夏休みにHotchkissでの新生活に向けた準備をしていた時の緊張感や不安感を鮮明に覚えています。テンスクールズの中でもCompetitiveな環境に純ジャパの僕が10年生から入学することはかなりのチャレンジだということを認識していましたが、その想像よりもチャレンジなことやステップアップしなければならなかったことが多かった1年でした。しかし、Hotchkissのアットホームで仲間と切磋琢磨しながら成長できる環境に身を置けたことで、日々学びが多く満足度の高い生活と経験を過ごすことができました。
特に英語の授業でのReadingとWritingの成長が1年を通して最も著しかったと考えます。英語の授業ではClose Readingという文章のひとつひとつの言葉の意味と文章全体のテーマを論理的に結びつけて読解をするという少しイレギュラーな授業の進め方に最初はかなり困惑してしまいました。常に100%ではなく150%を理解するReadingを求められて、純ジャパの僕にとってはひとつひとつの言葉が持つ意味をどう明確に解釈してテーマと結びつけられるかということをマスターすることに難しさを感じました。19世紀のプランテーションから逃れる奴隷の物語を描いた本Frederick Douglassでは、単語のUtopiaについての解釈をする際に単語の語源となったギリシャ語ではOuはNot、ToposはPlaceをそれぞれ意味し、奴隷の思うユートピアのように何もが完璧な世界など存在しないということを奴隷が自由になることがいかに難しいかというテーマと繋げることがありました。このような複雑なReadingに加えて、Writingではその読解したものを簡潔に自分の考えとともに結論に持っていく作業が求められたので、英語の授業はかなりのチャレンジでした。ただ、先に述べたように多くの生徒と切磋琢磨してお互いに学んでいける環境が魅力のHotchkissならでは、友達にReadingの解釈が論理的か否かや、自分の書いたエッセイが簡潔でわかりやすいかを確認してもらい、ReadingとWritingのスキルが大幅に向上したと感じています。
一方で2年目以降改善すべき点として、助けを積極的に自分から求める力を養っていくべきだと思います。Hotchkissでの教育はいい意味でも悪い意味でも放任主義なので、我々生徒も自分で考えて選択をして行動をすることが多いです。僕の以前行っていたジュニアボーディングスクールでは中学生ということもあって大人の監視が強く、常に心配事がないかや困っていることがないかなどと生徒と確認をすることが多かったのに比べ、Hotchkissでは自分から助けを求めて行動しないといけなかったことに気がつくのが少し遅かったと考えます。特に英語や歴史のクラスなど純ジャパの自分にとってチャレンジなクラスの先生のOffice Hourにもっと積極的に行けばより苦手分野の克服が早かっただけに少し後悔はしています。放任主義とはいえ、学校中に問題解決のプロの大人や優秀な生徒が多くいるので、そういったチャンスをうまく利用できなかっただけに2年目以降は助けを求めることを躊躇しないことを目指したいと思っています。
正直な1年目の感想としてはあっという間に過ぎてしまい、忙しさも相まって休んでいる暇はないということに尽きます。最初のうちはこの忙しいスケジュールと大量の課題に弱音を吐いていましたが、1年経った今はよくわからないモチベーションとともに頑張れています。2年目以降も様々なチャレンジに直面すると思いますが、それを克服する過程、成長できる環境にいることに感謝をして学校生活を楽しんでいきたいと素直に思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。日本に帰ってきて毎日のように酷暑で倒れそうになることで、冬でも半袖半ズボンで過ごす僕がいかにNew EnglandのHotchkissの気候にあっているか実感した今日この頃です。